【子どもの準備8】頭のいい子に…親にできることは?
勉強だけしていると危ない!
多くの小学生が塾に通っている今、わが子の成績が気にならないママ・パパは少数派でしょう。でも、教育の現場にいる先生方にうかがってみると、教育熱心さが空回りして、むしろ子どもの勉強意欲を阻害してしまっている親御さんが案外多いのだそうです。
良心的な塾講師やプロ家庭教師のアドバイスはだいたい同じです。「小学校低学年のうちから1日何時間も机に向かって、遊ぶことなく体も動かさず、お手伝いもせずに過ごしていると高学年から中学校にかけて成績が伸びなくなります。低学年のうちは、とにかく生活感覚・身体感覚を磨いてほしいですね」とのこと。
【子どもの準備7】でも書きましたが、生活感覚・身体感覚とつながらない知識は、テストが終わると忘れてしまう一夜漬けの記憶のようなもの。それに対して小学校低学年のうちに身につけたい学力は、テストがあろうとなかろうと、その子の心身に根づいてほしい土台の基礎学力です。基礎学力には生活実感が深く関係していて、その土台の上でなければ、より高度な知識や教養が育まれません。
大きくなっても成績のいい子になってもらうために、小学一年生のママ・パパはどうしたらいいのか? 教育現場の先生や教育評論家のアドバイスをまとめてみました。
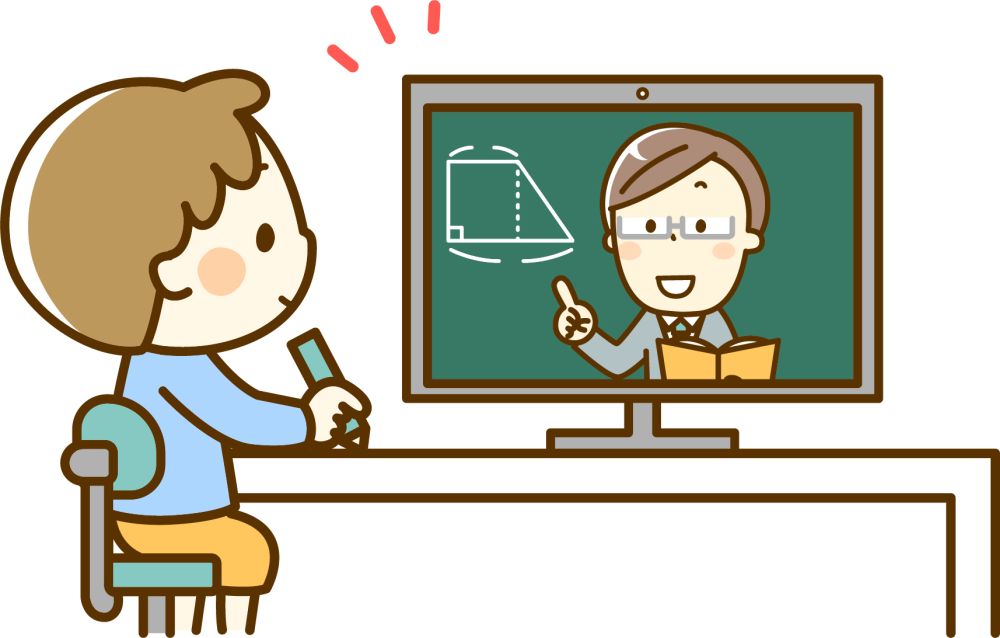
鍵は「勉強好き、考える力、集中力、生活感覚、長期展望」
小学生になったお子さまに対して、以下の5つのアプローチを心がけてみてください。
1,勉強が好きな子にする
好きなことは覚える、嫌いなことはすぐに忘れる――これは、大人も子どもも同じ。ママ・パパ自身、子どもの頃覚えたことで今も身についていることと、すっかり忘れてしまったことがあると思います。子どもの覚える能力はとても高いので、親に覚えなさいと言われれば一旦は覚えますが、関心を失えばすぐに忘れてしまいます。
そうならないために、勉強の内容が面白い、好きと思えるような環境や素材を用意してください。楽しみながら覚えたり考えたりできれば、必ず身につきます。まあ、最初からすべての教科が好きになるというのは難しいでしょうから、まずは、お子さまをよく観察して、好きになりそうな教科からスタート。勉強が遊びと同じくらい楽しく思える環境作りを心がけてください。
2,生活感覚を育てる
遊びやスポーツ、お手伝いで体を動かすことはとても大切です。勉強とは一見無関係なように思えますが、実はその逆。知識は実感を伴って初めて、しっかり頭の中に根づくからです。一緒にキッチンに立てば、学校で教わった植物と食卓の野菜が結びついていきます。「あれ、これ学校で習った○○と似ている!」などと気づくことが大切です。一緒に図鑑を見て、なるほど同じ仲間の植物なのね…と、知識の幅を広げていきます。
今の時代、生活感覚や身体感覚を磨く機会はそれほど多くはありません。便利な道具が簡単に手に入り、創意工夫が必要なことも、昭和の時代と比べるとめっきり減っています。そのため、子どもにさまざまな体験をさせるためには、「わざわざ」する必要がでてきました。お手伝いからアウトドア体験まで、面倒と思うことも多いと思いますが、子どもを賢くするためと考えて、子どもにいろんな体験の機会をつくってあげてください。体を動かして身につけた知識は、しっかり脳に定着するのですから。
3,今すぐの成績より将来の好成績を目指す
小学一年生の段階では、成長度合いに大きな個人差があるので、成績を周囲の子と比べたところで意味はありません。その時々のテストの点で一喜一憂することは慎みましょう。
今のうちは、テストや通知表の結果は参考程度にして、子どもの日常の言動から1年前からどれくらい成長したかをチェックしましょう。1年前から順調に成長していれば、心配することはありません。周囲と比べて成長が遅いかなと思ったら、“英雄にありがちな大器晩成”ということで納得してください。実際、歴史を振り返ってみても、大器=英雄の多くが、幼い頃できの悪い子だったのですから。
4,考えるのが得意な子に
1にも書いたように、人間、一度覚えても忘れることがたくさんあります。でも「考える力」は、身につくと一生ものです。
「考える力」の育て方で、いちばん簡単な方法は、「なぜ?」を大切にすることです。
子どもは皆、疑問のかたまり。いろんなことを、「なぜ○○なの?」「どうして××になっているの?」と聞いてくることが多いと思います。そういうときは、絶対に拒否しないで一緒に考え、できれば一緒に答えを見つけるようにしましょう。いちばんいけないのは、「そんなこと考えたって無駄よ」などと言って疑問を抱く芽を摘んでしまうこと。またテストのように、こういう問題の正解はこれといった暗記式の教え方もよくありません。どうしてこれが正解になるのかを親子で一緒に考えるようにしましょう。
中には、答えがすぐに出ない、親もわからない、といった疑問も出てくるでしょう。それはそれでいいのです。「わからない」という認識こそ、考え始めるスタート地点だからです。まずは、このスタート地点に立つ機会をできるだけ増やすようにしましょう。そうでないと、考える力を育てるチャンスも減ってしまいます。「わからない」と思った瞬間から、人間の脳は、ああかな?こうかな?と考えることを始めています。ただ、大人の中には、わからないことはすぐ忘れるクセのついている人もいるのでご用心。
わからないことはわからないことと自覚し、忘れないで、折に触れて考えたり調べたりするようにすればよいのです。きっといつか、答えが見つかります。そんな長期計画で臨んでください。ローマならぬ、「ノーベル賞受賞者は、1日にしてならず」です。
★こちらのページも参考にしてください→「考える力」を育てる「家庭の力」
5,好きなこと、夢中になれることを見つける
1に、好きになれそうな教科から始めましょうと書きましたが、何も授業の科目だけではありません。何かあるジャンルを好きになることがとても大切です。何かに夢中になるという集中力も、子どものうちに獲得したい貴重な能力だからです。お稽古でもスポーツでも読書でもその他なんでもOK。
親や周囲から「しなさい」と言われたことをきちんとこなし、素直ないい子と言われて育った子が、思春期になって、「私は何がしたいのかわからない…」と無気力になり次第に落ちこぼれていくという話を聞いたことはありませんか? これが、自分がしたいこと、好きなこと、夢中になれることを見つけることなく成長した悲しい結果です。
おすすめは、博物館や美術館を積極的に活用すること。子どもの興味を引くものがたくさんあり、好きなものが見つかる可能性が高いからです。日曜日や長期休暇にはぜひ親子で出かけていって、一緒に驚いたり楽しんだりしてみてください。
これからの時代、学歴も一生の保証にはなりそうにありません。自分で好きなことを見つけて、好きだからこそ頑張るという生き方ができないと、これまで以上に生きづらくなりそうです。
お子さまには、夢中になることを見つけられるように、いろいろな体験をさせたり、何もしないでいい自由な時間をたっぷりとったり、ぜひ好きなことを見つけやすい、ゆるやかな環境を作ってあげてください。
★こちらのページも参考にしてください→プロ家庭教師・西村先生がアドバイス 「小学校入学前の親たちへ」
2023/11/28